【箇所】一橋大学 国際・公共政策大学院 公共法政プログラム
一橋大学大学院 法学研究科 修士課程・博士後期課程
【科目】行政学Ⅰ・基礎:行政学特殊問題第一
【開講学期】2011年度 夏学期[2単位]
【担当】辻 琢也 教授〈一橋大学大学院 法学研究科〉
【課題】西尾 勝『行政学』[新版](有斐閣、2001年)の各章を読んで自らが考えたこと(第6章から第8章)
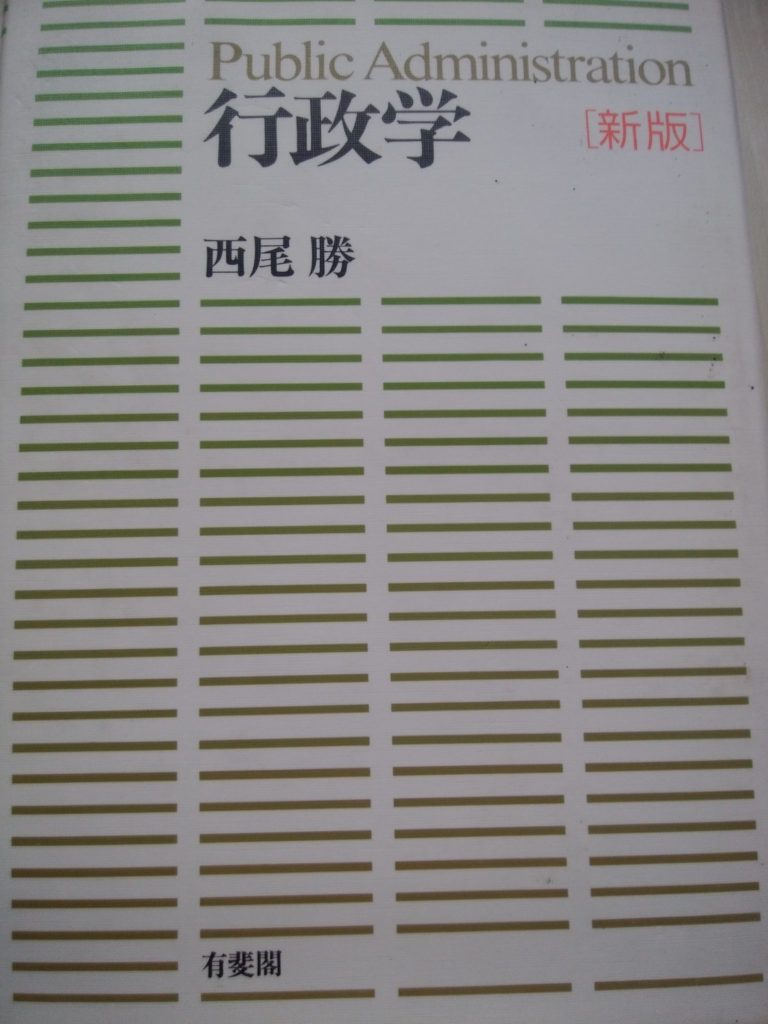
第6章 戦後日本の中央地方関係 72-96頁
指摘:79頁 第2段落における「機関委任事務」に関する記述について
機関委任事務という文言は、宮澤俊義教授が命名したということをきいたことがあるが、今回それを確認することはできなかった 。
その機関委任事務は、「地方自治法制定の当初から、問題の発端が内在されていた。いいかえれば、現行の地方自治が確立した時点から今日まで潜伏している宿痾となっている」 と説明されるほど、地方自治にとっては阻害要因とされていたものであった。
今日このように説明されている、機関委任事務制度を、「市町村長を自動的に地方行政官庁に準ずる国の地方行政の機関にするという機関委任事務制度が採用された」としている記述は、後世における説明においては何ら問題のないものであるが、明治時代の地方制度の構造を説明する際には、明治時代にこの機関委任事務制度が、どのように説明されていたのかを、明らかにしたうえで、その文言を使って説明しない限り、時代性に即した記述とはいえないものと考えられる。
そこで筆者であるならば、次のような記述をおこなうことになる。
今日でいうところの「「機関委事務」こそは、当初に内閣法律顧問モッセがプロイセン・ドイツをモデルに示唆したしくみで、市町村行政を国策的に活用する名案と考えられたものであった」 が、「これは、本来的には国の事務に属するものを「地方公共団体の行政機関」の手を借りて処理するというものである。したがって、知事・市町村長などの地方公共団体の行政機関は、この事務を処理する限りにおいては、いわば国の行政機関の一部に組み込まれるものとして扱われ」 るものである。
「1886年(明治19年)の地方官官制という勅令で、ふつう内務省官吏である府県知事が国の総合地方出先き・地方行政区画である府県の長だとされていたが、1890年(明治23年)法律の「府県制」によって、三府四三県に「一定ノ範囲ニ於テ……一ノ自治体」としての位置づけを与えてもいる(美濃部達吉『改正府県制郡制要義』明治四〇年版二三頁)。府県に法人格を認め、条例規則制定権を明記したのはその後の改正による(それぞれ明治32、昭和4年改正)。このように第二次大戦前の府県は、自治体の一面を持ちながらも全体としては国の地方出先機構なのであり、市長や市に対する監督機関なのであった」 。
上記のように記述したほうが、筆者にとっては、よりよいように思われる。
第7章 議院内閣制と省庁制 97-131頁
指摘:内閣主導の「政治主導」が実現されていない理由が記載されていない。
本章リードに、「本章におけるメッセージは、「政治主導」とは、政治家主導や与党主導のことであってはならず、内閣主導のことでなければならない、ということである」との記述があるが、それならば、どうして「政治主導」がなされなければならないのか、といえば、「明治憲法から新憲法への憲法改正が日本の統治機構にもたらした最大の変革は、国民主権を宣命し国会を国権の最高機関にして、議院内閣制を確立したことである」 ため、憲法65条に「行政権は、内閣に属する」とあるとおり、行政機関は例外なく内閣におかれたように、新憲法の理念を実現させるうえで、内閣主導の「政治主導」が実現されなければならないと著者は考えた。
このことは、次のようにもいえるものと考えられる。「憲法に定められた統治機構の外にある政治家や政党が、与党審査という名の下に、憲法に定められた統治機構である内閣、さらには国会における政策決定を左右していることは、政策決定過程を不透明にし、政策決定の責任の所在を不明確にしている点で極めて問題が多いとともに、国政のグランドデザインを提示することなく、部分利益の擁護に終始する「分配の政治」の存続にもつながるものである」 との指摘と同工異曲をなす。
ところが、日本では、与党と内閣が一元化されていないため、「政治主導」が実現されていない。
その理由は、筆者が考えるところ2つあり、本書にはそのうちの1つだけが記載されている。それは、「自民党議員に限らず、およそ国会議員である者は皆、みずからの地元選挙区の後援者からの要望や政治献金を提供してくれる支援業界からの要望に応え、これらの要望を関係省庁の官僚制組織に仲介斡旋することをその生業にしてきた」 ため、むしろ政治家自身が「政治主導」を望まなかったからである。それゆえ「政治主導」が実現されていないというのが、理由の1つである。それを本章では、「議院内閣制の制度原理に照らせば、与党機関と内閣・各省庁の政府機関とは二元的に分立していて、両者が「政権」に一元化されていないところにこそ、戦後日本における議院内閣制の制度運用の特異性があらわれている」 という記述をもって指摘している。
あとの1つは、現今の政治家が「政治主導」を唱えるようになった経緯である。日本は本格的な少子高齢社会となったことにより、税収が今後ますます減少してしまう。そこで、政治家は恩顧主義による、「利益分配」をし難い状況が現出したこと により、与党であっても恩顧主義を働かすことができにくくなったため、与党と内閣を一体化させることを画策するようになった。
つまり、政治家は、与党と内閣を一体化させなければ、恩顧主義を図って、選挙で自らが当選を果たすという欲求を満足させることができなくなったため、今になって「政治主導」に本腰をいれるようになったのではないか、と筆者は指摘する。
第8章 現代公務員制の構成原理 132-160頁
指摘:公務員制度の抜本改革に資する視角を著者は提示していない。
本書は、「はしがき」にあるとおり、行政学講義用の教科書として記述されたものなので、「制度学の視点からの考察を中心にしながら、これに多少は管理学と政策学の視点からの考察を加味したものになっている。」
本章は、リードにあるとおり、「国家公務員の一般職職員のうちの給与法適用職員にかかわる公務員制」について概説されたものであるが、上記にある、政策学の視点からの考察が、重要な論点においても加味されていないため、筆者はそれを補うべきものと考える。
それが最も気になる箇所は、「政治改革の流れは、いつの日か、公務員制度の抜本改革にまで行き着くことになるのではないか、と思われる」 という著者の指摘である。このような指摘を著者はしておきながら、それに関する管理学と政策学、いずれからの考察もくわえていない。これは、いくら制度学の視点からの考察を中心としている教科書とはいいながら、あまりに他人事のような態度といわなければなるまい。
あえて、管理学と政策学からなる視角に近い記述をさがすと、それは、次にあるような箇所が挙げられる。
148頁にある、「戦後日本の官僚主導体制の最大の弊害は、各省庁のセクショナリズム(分立割拠性)が異常に強固で」という箇所の次に、「見直しの矛先は各省庁の異常に強固なセクショナリズム(分立割拠性)の基盤になっているキャリアの各省別採用制度にまで向けられてきている」という記述がある。
そこで、思い出すのが、145頁にある、「イギリスの行政階級は、政府単位で一括採用され」という記述である。
先に引いたように、今ある政治改革の流れが、いつの日か、公務員制度の抜本改革にまで行き着くというのならば、ここでは、もう一歩踏み込んで、147頁にある「いまのところはどちらともつかず、理念の全く異なる対極的なふたつの型(イギリス型とフランス型)を曖昧なままに併用する方向に進みつつあるように思われる」といった高見の見物的な記述で終わらないで、日本でも、現在の採用?種試験に合格したら、本省庁によって採用することなく、イギリスのように、政府で一括採用することで、従来からある、セクショナリズムは打破できるのではないか、といった政策学からなる記述もくわえるべきものと、筆者は考える。
そうすれば、「ときたま人事交流で他省庁等に出向すること」 があろうとも、本籍が採用した省庁にあり、現住所が出向先といった、セクショナリズムに拘束されることはなくなり、省益より真の国益を目指す国家公務員が輩出することに資することになるものと、筆者は考える。




 Facebook [3ranjo]
Facebook [3ranjo] X(旧Twitter) @s_ranjo
X(旧Twitter) @s_ranjo Instagram
Instagram


 042-720-4644(留守電対応)
042-720-4644(留守電対応) 042-720-4644
042-720-4644