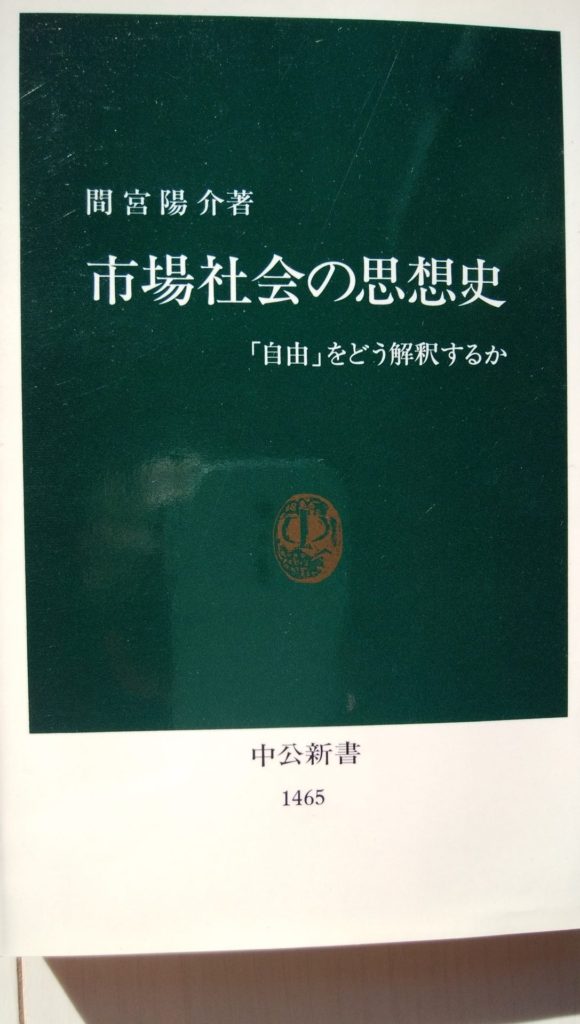
らん丈のウェブサイトにあるプロフィールをごらんいただければお分かりの通り、ぼくは41歳にして経済学部3年次に編入学しました。へん入学というぐらいですから、落語家としてはかなりヘンなおっさんです。
なにしろ、ぼくは文学部を卒業したことからもお分かりのとおり、経済にはまるで興味、関心がなかったのです。ところが、思うところ(町田市議会への立候補)があって、そのためには地方財政のことを学ばなければ、有権者に責任ある政策を提示できないと念じ、遅ればせながら、大学にもどり経済学(主に財政学)を学び始めたのです。
今年経済学部を卒業したものの、在学中は経済学史や社会思想史をカリキュラム編成の関係で修得できなかったので、入門書を探していたところ、信頼できる筆者=間宮陽介による格好の入門書を見つけたので、読み始めたところ、得るところが大きく、読み物としても実に面白かったので、今回の「らん読日記」では本書を採り上げました。
経済に興味のない方は、パスしたほうがよろしいかと、らん丈は思いますが、好かったらお付き合いください。
本書は間宮陽介(京都大学名誉教授、青山学院大学 総合文化政策学部 特任)教授が、放送大学での「経済思想」という講義科目を担当した際に執筆した講義用テキストであり、目指したものは「経済思想の網羅的な解説ではなく、いわば問題史としての経済思想史で」す。その問題史とは具体的には、副題にあるように、「自由」への対応を通しての経済思想史ということです。ここで、著者の間宮陽介教授をごく簡単に御紹介しましょう。同教授は昭和23年に長崎市で生まれ、東京大学経済学部を卒業後、神奈川大学助教授を経て、京都大学人間・環境学研究科教授を勤めた後名誉教授となり、青山学院大学教授となりました。専攻は社会経済学です。
稿は18世紀のアダム・スミスが「しじょう市場」を発見したところから起こされます。スミスは1723年にスコットランドのカコーディーという町に生まれ、1790年に亡くなりました。主著『国富論』が出版されたのは1776年のことであり、彼の生涯の後半期は産業革命の勃興期と重なっており、資本主義の確立に向けて時代が大きく変わっていく転換期にあたっていました。
さて、『国富論』です。スミスは同書で、富は貨幣(金銭)なりとして、金銀を蓄積することが国を富ませる方途だと考えた重商主義を批判し、国富は労働による年々の生産物から成ると主張しました。これが、後にリカードに継承され、マルクスによって完成された労働価値説として体系化されます。
同書で最も有名なのは次に掲げる一節でしょう。
「もちろん、かれは、普通、社会公共の利益を増進しようなどと意図しているわけでもないし、また、自分が社会の利益をどれだけ増進しているのかも知っているわけではない。……〔それはひとえに〕自分自身の利得のためなのである。だが、こうすることによって、かれは、他の多くの場合と同じく、この場合にも、見えざる手に導かれて、自分では意図してもいなかった一目的を促進することになる」(第4篇第2章、大河内一男監訳)。
経済学部に編入学し、アダム・スミスを知り、彼が唱えた個人の自己目的の追求が社会的利益を損なうどころか、むしろそれを促進するという命題を知ったときの驚きは、いまでもまざまざと覚えています。それをスミスは18世紀に提出したのですから、当時の人々にとってはまさに驚天動地の逆説的命題であったことでしょう。
ところで、『国富論』でのスミスの考えは、それに先立つ17年前に書かれた彼の『道徳感情論』(1759年)における説と矛盾するのではないかという疑問が早くから提出されています。というのもスミスは『道徳感情論』において「同感」という概念を据え、利己的個人を社会へと統合する原理をこの同感に置いていたからです。
この『道徳感情論』で、スミスは人間には、他人の運命に気を配り、その幸福を見ることを快いと感じさせる原理が存在すると述べています。
だからこそスミスはやや逆説的に次のように言います。
「あなたは逆境に陥っているのか。もしそうなら、孤独の闇の中で独りで悲しんでいてはいけないし、またあなたの親友達の寛大な同情によって自分の悲しみを調節してもいけない。できるだけ早く世間と社会の白日の下に戻りなさい。赤の他人、すなわちあなたの不幸について何も知らず、あるいは何ら気に留めない人々と生活しなさい」と。
これは、とりもなおさずわれわれは「独立した強い個人」として生まれたのではなく、独立した強い個人にならなければいけないという、スミスの励ましの言葉なのでしょう。
先ほどの「アダム・スミス問題」に戻れば、『道徳感情論』では正義の法の由来が道徳哲学として論じられ、『国富論』では自己利益の社会的利益への転化が経済学として論じられたと、本書で論じられていますが、正直のところぼくにはこの箇所はどうも納得できかねます。
いずれにしろ、スミスが道徳の基礎に理性ではなく感情を置いたのも、あるいは市場社会の構成原理として利己心や自愛心を考えたのも、突き詰めれば、人間は全知全能ではないという基本的認識があったからでしょう。
ここが、19世紀以降の新古典派経済学が人間を全知全能の経済人と規定するところと、まったく違うところです。
以上が、第一章「経済学の誕生」の梗概ですが、全15章から成る本書は、以後、反ケインズ派のマネタリズムや合理的期待学派が台頭する1970年代までの経済学の流れを追っています。
ほんのさわりしか御紹介できませんでしたが、最終章「経済学における自由の思想」までを通読すれば、経済学の流れが実にすっきりと頭に入っているのを実感できます。




 Facebook [3ranjo]
Facebook [3ranjo] X(旧Twitter) @s_ranjo
X(旧Twitter) @s_ranjo Instagram
Instagram


 042-720-4644(留守電対応)
042-720-4644(留守電対応) 042-720-4644
042-720-4644