【箇所】早稲田大学大学院 社会科学研究科 地球社会論専攻
【科目】社会哲学Ⅰ【開講学期】2007年度 前期[2単位]
【担当】田村 正勝 教授〈早稲田大学 社会科学総合学術院〉
【テクスト】田村 正勝『新時代の社会哲学』[新装版]−近代的パラダイムの転換(早稲田大学出版部、2000年)
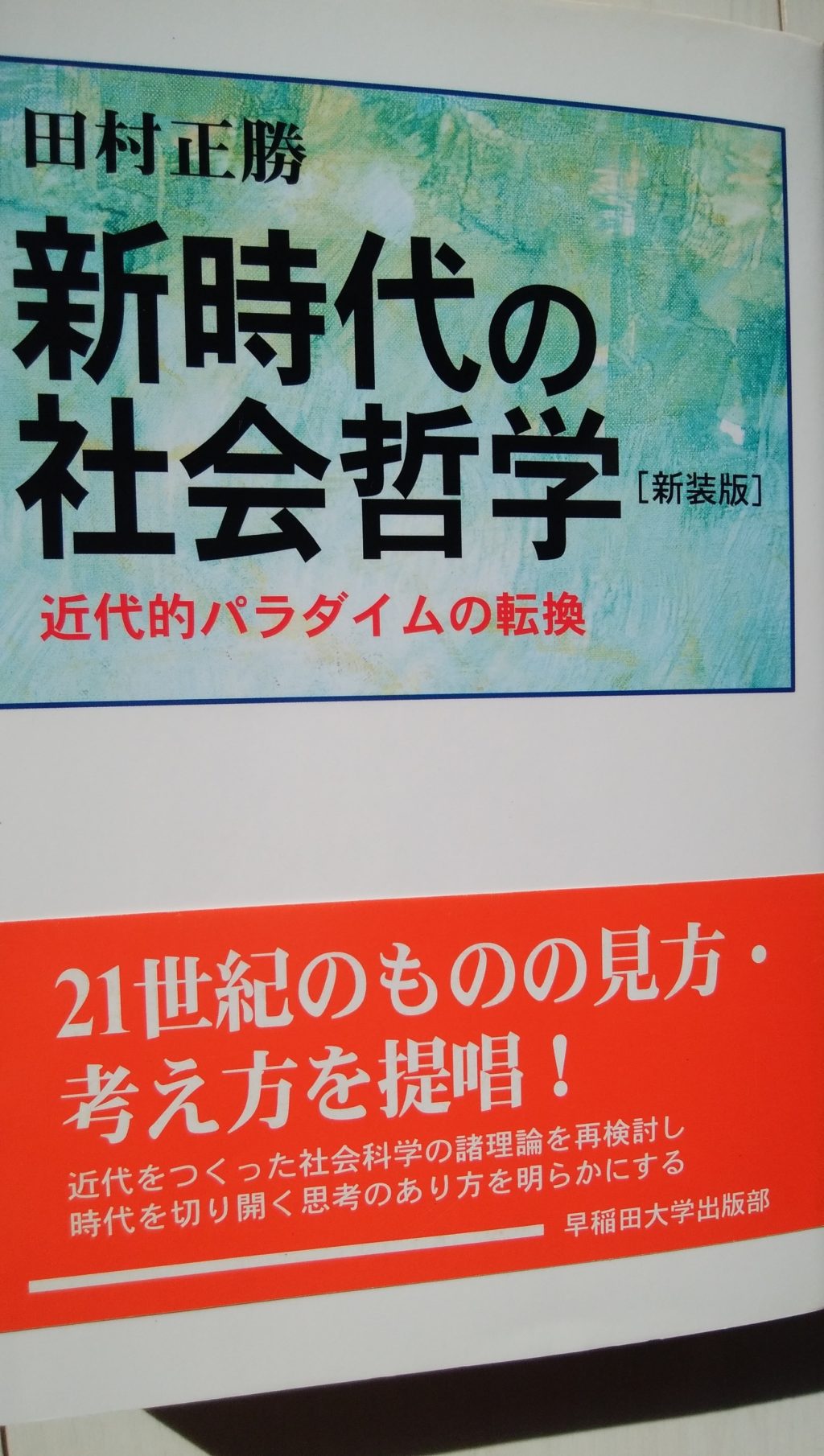
Ⅱ 社会科学の本質と課題
2 社会科学の主観性・客観性・実践性
5 政策論の定位 pp.159-162
政策論は、社会科学全体からみると、どのように位置づけられ、展開されるのか。
1、現時点から振り返ることによって、これまでの時間的空間的現実がなぜ生じたのかを問う。
歴史的に先行する事実が、なぜ生じたのかを説明するわけであるから、それは、史的限定性をもつ。
具体例として、本書では、ミュルダール[注1]が『社会科学の方法』で、科学はまず事実(facts)自体もしくは問題自体から出発する、と主張したことを挙げている。
[注1]ミュルダール:不況期に景気を刺激するための財政赤字を、好況期の黒字で相殺していく反循環政策を理論的に初めて支持したとされる、1933年の財政法案の付属文書を執筆した。これは、ケインズ以前のケインズ政策とも呼ばれている。
不況期の財政赤字に対する批判は、ピーコックとワイズマンが1890年から1955年までのイギリスの政府支出の長期的趨勢について、転移効果を指摘した。
転移効果とは、国民の多数が望ましいと思っている財政支出水準と受忍しうる課税水準の間には、通常隔たりがあるが、戦争等に直面すると経費支出も税負担も増大し、戦争が済んでも元に戻らず、経費は不連続的に階段状に膨張するとされることを指す。
同様の観点からは、ブキャナンとワグナーによる政治経済学的な立場からのケインズ的財政政策への批判もある。
それは、ケインズ的財政政策は、不況時には財政支出を増やし、景気過熱時には引き締めることが建前であるが、議会制民主主義のもとでは、財政政策の対称性が失われて、拡張的政策ばかり採用される傾向が強い。
その結果、公共部門が必要以上に肥大する。したがって、ケインズ理論は現実の政治経済学としては有害である、というもの。
あるいは、バローなど新リカード主義による批判もある。
それは、「バローの中立命題」と呼ばれるもので、合理的な個人は公債が発行された場合、その利子支払および償還が将来の増税によって(あるいは将来の政府支出削減によって)まかなわれることを予想する。
その結果、公債の発行は将来の増税(もしくは所得減少)と同一視されるであろう、という論理。これは、結局先の世代のことまで間接的に関心をもつために、いくら公債の償還が先送りされても、人びとは自らの生涯の間に償還があるときと同じように行動する。
公債発行と償還のための課税が同一の世代の枠を超えても、公債の中立命題が成立する。
このバローの中立命題の問題点は、現実の経済が複数の家計からなることを無視していることにある。
複数の家計の存在する社会では、所得の違いにより、税負担も公債保有状況も異なるので、親が子供のことを考慮して行動するとしても、かならずしも租税と公債が中立的な経済効果を持つ保証はない。
もうひとつ、フリードマンの新貨幣数量説による批判もある。
それは、国債の大量発行により、市場の資金が吸い上げられ、金利が上がり、民間の必要資金が調達できなくなることを指摘するものであるが、マネタリストは、これによって民間投資が抑制され、財政による有効需要増大効果が相殺されるとして、ケインズ的政策に疑問をなげかけるものの、そこで起こるとされるクラウディングアウトは、過去に日本でも米国でも招来された事実はない。
ミュルダールの『経済学説と政治的要素』(1930年)の訳者は、山田雄三[注2]と佐藤隆三。訳書は1967年の発行であるが、原著はドイツ語であり、1953年版の英訳からの翻訳。
[注2]山田雄三は、先頃物故なさった作家、城山三郎の東京商科大学(現一橋大学)在籍時以来の恩師としても、その名を江湖に知られる。
その城山三郎に、「山田教授の生き方・考え方」という副題をもつ、『花失せては面白からず』(角川文庫)という著作がある。
山田ゼミのテキストは、モルゲンシュテルンとノイマンによる共著『ゲームの理論と経済行動』(1944年)だった。
同書によって、相手の行動を予測して自らの行動を決めるという経済行動を仮定し、ミクロ経済学の新しい分野となった、ゲーム理論と期待効用理論が切り開かれた。
ウォーム・ハート[注3]を求めて、山田ゼミに入室した城山にはそれがまもなく物足りなくなった。
「現実はさておき、数字にはじまり、数字に終わる。きらびやかな世界の中だけの舞い。空の舞台で空しい舞いを舞うだけ。その自己満足でいいのか。いや、満足どころか、不満を溜めるだけにならないのか」
そう思った城山は、山田宛に、ゼミをやめさせてもらいたいという手紙をだす。クール・ヘッドは感じられるが、ウォーム・ハートに欠ける学問だと思ったからだった。
それに対して、山田から意想外の手紙が届く。城山にとって「いまも読み返す度に、それこそ胸の熱くなる手紙」だった。以下にその抜粋を載せる。
『詳しい御手紙で君の心境がよくわかりました。どうか自由に君は君の道を進んで下さい。
ただ社会科学者として、この際一言私の考えだけを述べさせて貰いましょう。というのは、君が手紙のなかで述べているように、私は決して「淡然として」イデオロギーの問題を棄て科学的実証研究に安んじているのではないのです。シュムペーターのいうエントフィロゾフィーレン(哲学離脱)の主張に私は賛成しますが、それは断じてアンティ・フィロゾフィーレン(哲学排斥)ではありません。社会科学の研究者もまた結局は人間探求をやり意味把握をやっているのです。ただそれはあくまで実証研究を通してであり、かかる研究の行動自体が哲学なのです。
そこいらの哲学者とか思想家と呼ばれている連中がとかく実証研究を見降して「深いもの」をつかんだと自負しているよりは、もっともっと苦しんでわれわれは現実の人間なり生活なりをつかもうとしているのです。如何にも、例えば経済学では、均衡とか独占とか価格とか特有な述語を使い、いろいろむずかしい形式化もやりますが、問題は栓ずるところ個人と全体との在り方や人間の行動の仕方を知るにあるのです。このことは教室で演習の際に折にふれて述べていたはずです。
不幸にして君が私の意図を十分理解されないでいることは残念です。』
[注3]ケインズがマーシャルを評したときの言葉。なお、ケインズの父はマーシャルと親交があり、ケインズは子供の頃からマーシャルに可愛がられていた。ケインズが経済学者となることを早くからマーシャルは望んでいたという。
2、経済政策などの政策論は、理論に基づいて現実を変革あるいは維持するための手段を研究し、これを実践する。
現実が望ましくないのであれば、その原因を除去するための手段を研究するし、逆に現実が望ましい場合には、その現実を維持し促進するための手段を研究し、実践する。
ここに、望ましいか否かの価値判断と実践倫理とが介入することになり、政策論は、純粋理論と次元の異なった複雑さと難しさが包摂されることになる。
たとえば、インフレは所得の不平等を助長するから、これを克服すべきだと考えた場合、所得の平等が価値前提となっている。そこで、「所得の平等」という価値理念を前提としていることが、まず言明されなければならない。
したがって政策論は、第一に価値理念を明確にし、第二に価値理念の妥当性の解明を果たし、第三に具体的現実の克服もしくは維持・促進といった3段階を踏むことになる。
6 理論と政策と史的限定性 pp.162-164
社会科学の理論や政策は、決して時間的空間的に普遍的なものでありえない。
歴史のなかの「一定」の時間・空間における社会的過程を説明するものが理論であり、同様にこの過程の方向性を変革もしくは促進するものが政策だからである。
たとえば、A・スミスやマルクスあるいはケインズの理論や政策も、そのような学問として有効であったが、それが今日でもなお有用性があるわけではない、というまさにそのことを意味している。
今日の日本でケインズ政策を採用し、公共投資を増大させても、その結果、財政赤字を累増させることになり、大きな乗数効果は見込めないために景気刺激効果もさほど期待できないであろう。
このように、社会科学は一方で「歴史的使命」を担ってはいるものの、他方ではこれを推進させることにより、自らが妥当性を失うといった「歴史的宿命」をも背負っているのである。
7 理論と政策の悟性的限界 pp.164-166
社会科学の歴史的な限定性と並んで、次元を異にする、もう一つの社会科学の限界も指摘することができる。
それは、社会科学に限らず科学は一般に悟性による認識に基づくが、こうした悟性認識が避けることのできない限界である。
悟性的認識は、分析的認識であるから、認識の対象を客体化し対象化して、分析つまり分割する。
こうして分割して認識することによって、社会をもその構成秩序を独立した原理として捉えるために、二分法による認識に依存する。
その結果、自由原理を柱とする自由主義社会か、あるいは平等原理を柱とする社会主義原理か、といった「体制論」を展開し、現実をこれに近づけようとする政策さえも導入されてきた。
しかし、このような社会秩序に関する思考が誤りであることは、これまでの経済社会体制の歴史が物語っている。
自由主義社会は、次第に平等原理を導入せざるを得ないし、社会主義社会も、自由原理を導入せざるを得ず、それを実行してきた。
ただ、この悟性認識をわれわれは手放すことができるのか。
トインビーが言うように、それを完全に手放すことはできない。
なぜならば、実在の多様性、さまざまな原理や法則は、悟性の働きによってのみ得ることができるからである。
しかし、この多様性が本来は統一されていることを理解する能力は、悟性にはない。これは理性に委ねられている。
政策論も科学である以上、これまで述べたような限界を持つために、これも「本質の知」である理性的認識によって補われなければならない。
8 理論と政策と歴史のダイナミズム pp.167-170
政策論を実行する場合、その実践には選択が迫られる。
では、どの実践を選択するか、換言すると、本来の統一性に接近するために、現時点でどの原理を最優先すべきか、それが問題なのである。
この選択を決定する要素は何か。
それは、第一に歴史認識である。われわれの社会が、歴史上のどこに位置し、どこへ向かっていこうとしているのか、という認識なしに、この選択を正しく行うことはできない。
加えてもうひとつは、実践倫理である。歴史認識に倫理的価値判断が加わることによってのみ、実践が可能となる。
以上のように理論が政策として応用され実践される際に、まず歴史的状況認識が不可欠とされる。
それゆえ社会科学の理論と政策および歴史は、ここに密接に関連している。
ミュルダールの「事実から出発する方法論」に関連して触れたとおり、社会科学の理論は、現時点に先行したところの歴史に対する、分析的な説明に他ならない。
つまり、過去の一定期間に生じた社会現象を、因果論的に説明することが理論の課題である。
政策とは、この理論を応用して、先行した歴史の方向性を、将来に向けて促進もしくは転換することを意図している。
次の歴史時点において、再び現在から未来点の間の歴史を説明する理論が必要とされる。
なぜならば、考慮しなかったファクターが入り込むために、歴史が政策の意図に反した方向へ動くことが、往々にして見られるからである。
そこで、なぜ政策の意図に反した方向に歴史が動いたのかを説明する理論が必要とされる。
そうして新たに生まれた理論に基づいて、再び政策が試みられる。
こうした試行錯誤の軌跡が、歴史を形成する。
社会科学の理論と政策および歴史は、このようにダイナミックに相互関連している。それゆえ、歴史は直線的ではなく、弁証法的な展開を示す。
【検討】
1980年代に端を発する英、米、日の規制緩和政策は、市民への貢献よりも、それに比して余りにも大きな弊害を市民にもたらしたことを指摘し、著者は郵政民営化には、反対の立場をお取りになっている。
2005年6月7日に、衆院郵政民営化特別委員会に著者は参考人として呼ばれた際に、以下のように発言している。
「民営化後は郵貯、簡保をやらない郵便局が増え、結果的に郵便局は減り、金融弱者が生まれる。公社のままでの改革がベストだ」
このように、郵政民営化の弊害は、分割民営化にある、と著者は指摘する。
簡保、郵貯、郵便事業が一体化しているからこそ、利潤を上げているのに、分割民営化は、郵便局の赤字化を生み、結果的に、税金の投入が視野に入る、間違った規制緩和というのである。
ここに、国鉄の分割民営化とは様相を異にする、郵政の民営化問題の要諦がある。
たしかにレッセフェールは、ケインズの登場によって息の根を止められた。
これを著者は、“歴史の弁証法的展開を無視して、歴史を単に逆転させることは不可能である。”と評する。
これからの日本を考えた場合、少子高齢社会が急速に促進されるのであるから、GDPは減少し、国力はほぼ確実に衰えることが想定される。
たとえば、株式会社化した英国のロイヤル・メールは、2007年に2割近い2,500もの郵便局を廃止させようとしている。
かつて25,000を越えていた郵便局は、すでに10,000局以上閉鎖された。
それでも、郵便局網の赤字幅は1週間あたり4,000,000ポンド(約10億円)に及ぶ。
政府は、2003年から続ける年間1億5千万ポンド(約375億円)の補助金を2011年まで延長することを決定。
情報技術や、機械化投資への貸付なども含めて最大で17億ポンドを援助する計画を持つ。[注1]
このように、ロイヤル・メールでは、郵便のユニバーサルサービスを維持させるため、株式会社化してもなお、多額の税金が投入されているが、どれほどの額の投入が適切なのかは、今後とも議論を続けるべき案件であろう。
そもそもの問題は、英国で、郵政を民営化させたのは成功だったのか、それとも失敗だったのか、という視点である。
民営化は兎も角、分割した結果、郵便局の赤字化を招いた弊害は指摘されねばなるまい。
筆者は、これからの日本は、市民と行政によるゆるやかな官民協働社会の発展が望ましいと考える。
そのためには、NPOを始めとする非営利組織とのネオ・コーポラティズム[注2]も視野に入れて、新たな公共の場を策定しなければならないのではないか。
[注1]朝日新聞2007年7月17日朝刊13版p.7
[注2]労働組合や経営者団体といった巨大利益団体が政府の公共政策の決定過程へ直接に参加し、その政策の執行に責任を負う、という仕組みのことを指す。第二次世界大戦後スウェーデンやオーストリアなどといった北中欧諸国では、この仕組みの制度化を通じて政治的な調和と良好な経済実績の維持を計ってきた。
1970年代に入って、その他の先進資本主義諸国においても経済危機の克服の手だてとしてこの仕組みの有用性が注目されるに至った。
しかし1980年代以降の、利益団体の排除を目指す新自由主義の台頭を前にして、衰退・崩壊しつつある。




 Facebook [3ranjo]
Facebook [3ranjo] X(旧Twitter) @s_ranjo
X(旧Twitter) @s_ranjo Instagram
Instagram


 042-720-4644(留守電対応)
042-720-4644(留守電対応) 042-720-4644
042-720-4644