【箇所】早稲田大学大学院 社会科学研究科 地球社会論専攻
【科目】社会哲学Ⅱ【開講学期】2007年度 前期[2単位]
【担当】田村 正勝 教授〈早稲田大学 社会科学総合学術院〉
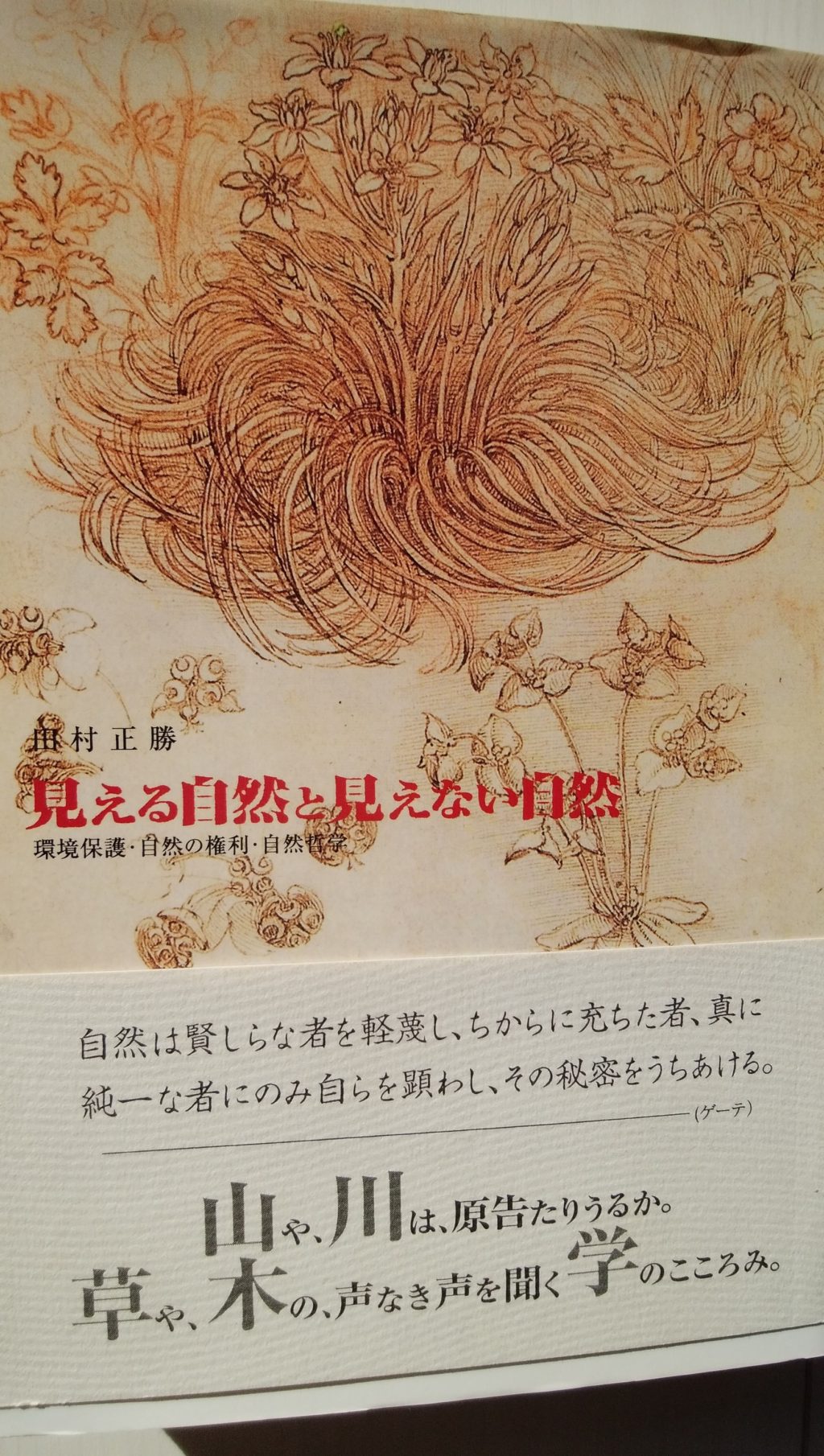
テキスト:田村 正勝『見える自然と見えない自然』環境保護・自然の権利・自然哲学(行人社、2001年)
序文
〔梗概〕
環境保護NGOなどが、自然を護るための訴訟を起こした。その際「原告適格なし」という理由で、そのほとんどが門前払いされてきた。
しかし「自然の生存権」が承認されれば、われわれは自然の代理人として、代理訴訟を起こすことができ、法廷はこの「自然の権利」の侵害について、実質審議に入らなければならなくなる。
じじつアメリカでは、「モートン判決」において、ダグラス判事の少数意見ながらではあるものの、「自然の権利」が可能だとする法理論が展開された。
本書は、この「自然の生存権」より端的な「自然の権利」を、いっそう根本的に「自然哲学」によって根拠づける試みである。
そこから自然環境保護の理念を、実践的かつ具体的に展開する。
その際、近代文明の中核にある自然観、「機械論的自然観」を、徹底的に反省しなければならないと著者は説く。
「機械論的自然観」とは、自然現象を「因果論」的に解釈するという意味のタームである。
したがってそれは、無数の自然現象をバラバラに切り離して、それらの各部分が、あたかも機械のごとく相互に関係していると理解する考えに基づく。
これに対して近代以前の自然観においては、個々の自然現象の背後にあると思われる「全体自然」が、最重視されたという。
本書の根底を支える思想であるドイツ自然哲学は、諸現象の背後で共通に働いている「自然の力」あるいは「永遠の生命の流れ」を検討してきた。
したがって本書は、すべての現象に通底する「永遠の生命の流れ」があるものとして考察されている。
本書第一章では、哲学を援用し、集合的な力である普遍性や共通性に光をあてて、タイプ分けし、その意味を解明する。
第二章は、ドイツ自然哲学の系譜を考察し、哲学の意義を明らかにする。
フランスの大陸合理論とイギリスの経験論の後を追うドイツ哲学は、自我の哲学から、自我の背後にある普遍性を掘り出し、これを提示する哲学であり、それを実践したカント、シェリング、ヘーゲル、フッサール、ハイデガーらの足跡を浮き彫りにする。
第三章では、「自然観と技術観の関係」を、哲学的にではなく、社会的および歴史的に考察する。
これによってドイツ自然哲学の背景と意義が、さらには自然哲学による「自然の権利」の基礎づけの意義も、よりいっそう明らかにされる。
最後に補論では、第二章および第三章の全般に関係する研究会報告と、それに対する質疑応答を掲載する。
〔検討〕
1、 著者は、「永遠の生命の流れ」を、ドイツ自然哲学を援用することによって、それを解明しようと試みるが、p.5の第3パラグラフで、ドイツ自然哲学と同じように、仏教も、人間と自然との関係を「存在論的」に深く考察している、と記している。
このことから、ドイツ自然哲学と仏教とは同じように、人間と自然との関係を捉えていることがわかる。
ならば、日本人には、ドイツ自然哲学よりはるかに人口に膾炙している仏教をもとに、人間と自然との関係を「存在論的」に考察したほうが、日本人の読者には説得力と親密性が増したのではないだろうか。
2、「人間の実生活は、科学的な因果論より、形而上学的な物語に、より広範囲に影響されていると言えるから、人間は、本質的に形而上学的思考の動物である。」と、著者は記す。
しかしこれを、「人間の実生活は、科学的な因果論によって規定され、形而下的な物語に、より広範囲に影響されていると言えるから、人間は、本質的に形而下的思考の動物である。」と書き換えても、なお、そのとおりだ、と思わせる人間がいるのではないかという疑念を、評者は抱く。
第一章 環境権と自然哲学―「自然の権利」の哲学的基礎づけ
一 環境倫理と環境保護条約
(一) 環境権と自然の権利の問題状況
〔梗概〕
今日もっとも大切なことの一つは、自然の破壊をできるだけ少なくし、自然を護っていくことである。
その実践にあたっては、エコロジーの知識と、自然の「存在論的」な把握の双方が役立つ。
エコロジーとは、自然の各部分をバラバラに取り出す個別還元論的な機械論的自然観でなく、自然全体を有機体とみなして、自然の各部分の相互関係を重視する自然観から成り立っている。
しかしこのエコロジー的自然観も、機械論的自然観と同様に、自然現象についての因果論的な理解である。
これに対して、「存在論的自然観」は自然現象の直截な理解ではない。
それは、因果律にしたがう自然現象の根拠を、目的論的に把握する自然観である。
これは、ジン(共)エコロジー(Synokologie)の見解であり、生物群それ自体のために生物群を問題とする。
同時にこれは、自然の内在的価値を認める視点であり、カント、シェリング、ヘーゲルやゲーテの自然哲学に繋がっている。
この立場は、人間の「自然との共生的な本能」を主張する。
これはまた、現在でこそ、われわれの経済活動が、森林を破壊し、湖や河川を汚染し、湿地帯を干上がらせているという認識を持つにいたっているが、それは人間の本来的な本能や衝動とかけ離れていると捉える立場でもある。
現実には、自然環境の破壊は、なお至るところで行われている。
とくに問題なのは、河川やダムや堰をつくるなど、広範囲かつ被害者が特定できない自然破壊となるような行政活動である。
これは、フランスやアメリカとは違い、日本ではまだ環境権が判決においては、認められていない現状があることに由来する。
米仏両国の状況を踏まえて、環境に対する権利「環境権」を、自然自身の生存権である「自然の権利」にまで発展させる思想や訴訟判決が日本でも出てきた。
例として日本では、「アマミ自然の権利訴訟(アマミノクロウサギ訴訟)」が有名である。
古代ギリシャの自然哲学やドイツの自然哲学、あるいは仏教における自然観などは、人間と自然との関係を「存在論的」に深く考察している。
エコロジーの視点は、この自然哲学などの「存在論的」な理解によって基礎づけられ、深められることが必要とされる。
なぜならば従来からある「自然の権利」の主張は、そのような「存在論的自然観」の視点に欠けているために、「自然の権利」と一般の法や権利との間を結ぶ論理が不明瞭となってしまうからである。
しかし、自然破壊が進展している今日、自然哲学とエコロジーおよび法律論の総合的な視点から、「自然の権利」の確立が考えられるべきである。
(二)環境倫理と環境権の変遷
「自然の権利」に関する理念こそが、自然環境の保護と環境倫理の根底になくてはならない。
その「自然の権利」を実践するために、第一に誰による価値判断か、第二に何を対象とする価値判断か、第三にどのような理念や脈絡における判断かの3点を明らかにすることが、重要である。
その第一は、個人の判断に基づく。
第二は、自然の恩恵を対象とする。この場合の自然とは、生物、無生物、景観、公園等「最広義の自然」を対象とする。
第三は、個人的な自益的権利であり、それは「基本的人権」に含まれる。
この環境権は、自然破壊が進むにつれて必然的に、いっそう広く展開してくる。
さらには、環境権は、「現在の人類共通な権利」、そればかりか「将来世代を含む人類全体の利益のための権利」と考えられるようになってきた。
こうして、環境権は、個人的な生活、現在の人類全体の生活、将来世代を含めた人類全体の生活へと展開してきた。
環境権は、実質的に人類の「環境保護義務」に変容したことに、注目すべきである。
これは、近代思想の黎明を告げた自然権が、権利であると同時に義務でもあるという内容であったことを思い出せば、権利ばかりでなく義務も生じるという環境権は先祖帰りを意味する。
(三)自然環境の保護理念「人類共通の利益」の限界
「環境権」を保護するのは、人類の「共通な利益」さらには「共同遺産」だからである。
では、共通の利益もしくは共同遺産の内容は何か。
第一に、「生態系」であり、これは人間の生存基盤である。
第二に、自然が、人類の経済活動の資源として役立つことである。
第三に、自然から「科学的な情報」という人類共通の利益が得られることである。
ただし、自然は「共通の利益」ゆえに保護すべきだという理念にとどまる限り、必ずしも自然は充分には保護されえない。
なぜならば、直接的な利害関係の有無があるかないかで、自然保護が左右されてしまうからである。
また、この自然保護という理念は、功利主義に頼っているかぎり、その狭隘さのゆえに自然が破壊されることをも招いてしまう。
あるいは、共通の利益といった曖昧性は、われわれの意識転換を鈍らせてもいる。
(四)人間中心主義を超える「環境保護」条約
環境権や自然保護に関して、人類共通の利益をそこに求めようとすることによって招来される陥穽は、「人類共通の利益」が、自然の中で人間だけが特別な地位を占め、人間に自然が奉仕する、あるいは自然を、そのために人間が支配すべきだといった「人間中心主義」の思想をもたらすことである。
この陥穽を招くことがないように、「人類共通の利益」という理念をも超えて、自然そのものに権利主体の性格をみとめる環境保護にかんする条約が生まれた。
それが、1982年の国連総会で米国以外の各国に承認された、「世界自然憲章」である。
この憲章では、「環境」という言葉を使うことなく、その代わりに「自然」という言葉に換言している。
ここにこそ、人間中心主義からの脱皮が象徴的に見て取れる。
〔検討〕
1、評者は、町田市廃棄物減量等推進審議会委員を勤めた際、町田市長から、町田市内から排出されるゴミを抑制する方策を諮問された。
それを受けて、ゴミ収集の有料化が最も適当であるとする答申を出した。
この答申を受け、町田市では2005年10月1日から、ごみ収集の有料化が始まった。
その結果、従来はゴミとして排出されていた紙等の資源は、無料の資源収集に大幅にシフトさせることに成功し、あわせて生ゴミ等の有料収集の対象ゴミを劇的に減少させることにも成功し、全体としては少なからぬゴミ排出抑制を実現させたことがある。
町田市では、ゴミ収集有料化以前から、ゴミ排出の抑制を市民に呼びかけていた。
その際、その文言は、自然環境保護のためにもゴミ排出を抑制しようということで、告知活動をしていたものの、結局功を奏すことはなかった。
ところが、ゴミ収集有料化を始めたその刹那から、町田市民はゴミ排出の抑制に躍起になった事例から、評者は、筆者のように形而上的な自然保護思想は、なかなかその核心が市民に理解されにくいのではないか、との危惧を拭い得ない。
2、形而上的な環境保護政策をとることで、逆に、一般市民の環境保護への注意、喚起に失敗し、それが、環境破壊のさらなる進捗をもたらすのではないか、との疑念が評者には生じた。




 Facebook [3ranjo]
Facebook [3ranjo] X(旧Twitter) @s_ranjo
X(旧Twitter) @s_ranjo Instagram
Instagram


 042-720-4644(留守電対応)
042-720-4644(留守電対応) 042-720-4644
042-720-4644