その本が面白ければ、自ずと読む速度が速くなるものです。つまり、面白さと読む速度は正比例にあるといえましょう。
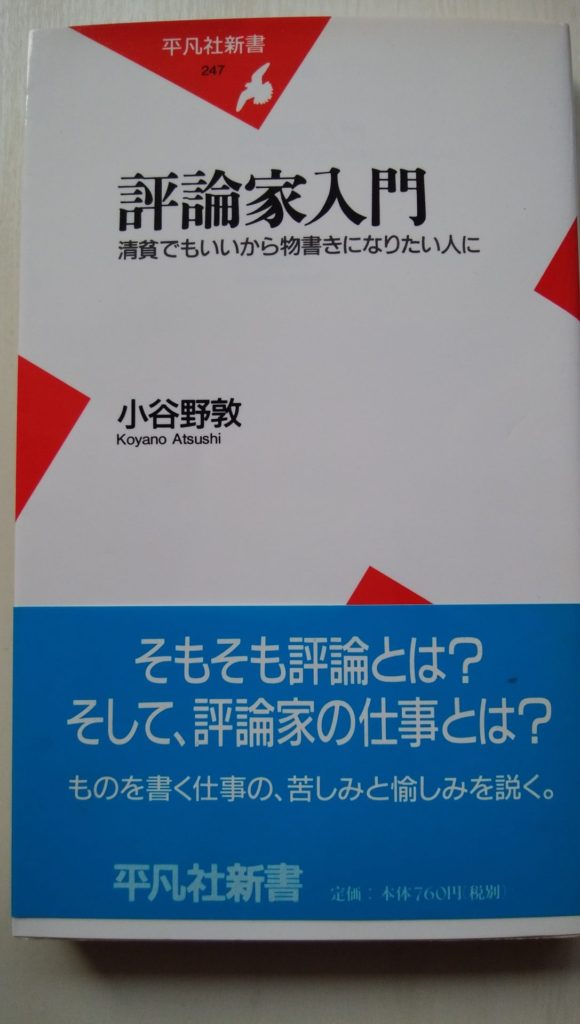
もちろん例外はいくらでもあります。たとえば、マルクスの『資本論』は19世紀中期までのイギリス資本主義経済を分析対象とした社会科学上大層有用でかつ、実に面白い著作ではありますが、あれをスラスラと読むことは、到底ぼくには不可能です。
あるいは多くの哲学の書物群も、然り。
この本は新書の形態をとっているのでもともと読みやすいうえに、小谷野の著作だけあって滅法面白く、じつにすらすらと頁を繰ることが出来ました。
では本書のどこが滅法面白かったのか。「身も蓋もない記述」の数々です。
たとえば、表題と最も関係のある言葉、「評論」を小谷野はこのように、定義する。「カネになる文章のことなのである」と。
どうです。身も蓋もないでしょう。ここに小谷野の真骨頂があるのです。
そして本書の白眉は、『バカのための読書術』(ちくま新書)にあった「読んではいけない本」リストを改めた、どこがどう悪くて、しかし見どころはどこか、という「採点!有名評論」です。
そこでは「有名評論」を5段階にランク付けしており、それは以下の通りです。
A:学問でありながら評論でもあって、こういうものを目指してほしい
B:学問的価値は疑わしいけれど、評論としての魅力が大きい
C:まじめに書かれてはいるのだが、学問的に否定されている
D:読むとそうかなと思うが、あやしい
E:明らかにひどい
ここで「A」の評価をしているのはわずかに、井上章一『法隆寺への精神史』(弘文堂)が一冊あるきりです。
反対に「E」評価はぞろぞろある。
吉本隆明、岸田秀、中沢新一、丸谷才一、土居健郎という何れも名だたる面々が、軒並み「E」です。
たとえば、土居健郎の『「甘え」の構造』を、“ほんとうにみんなこの本を読んで、面白い、とか、すごい、とか思っているのだろうか。”と評し、丸谷才一の『忠臣蔵とは何か』に至っては、“恐らく、近代日本の「評論」史上、文壇での高い評価と裏腹の中身のひどさという点ではワーストだろう。”ですから、快刀乱麻を断つ趣さえ醸します。
古来、悪口は蜜の味、というぐらいですから、たしかに他人(それも有名であればあるほど)の酷評ほど面白いものはなく、特に小谷野は情け容赦のない評価をさせたら右に出るものはいないのですから、つまらないわけがなく、だからというわけでもないのでしょうが、褒めるときには反対に著しく精彩を欠く。
たとえば、「学者分類の試み」で、A:文句なしに偉大な学者、で採り上げた日本人に関しては、“白川静、宮崎市定、中村幸彦、廣松渉といったあたりか”という素っ気無さ。
ただ、小谷野がほとんど評価しない丸谷才一と小谷野に共通するのは、戦後の文芸評論において、神の如く文壇に君臨した小林秀雄のダメさを指摘することです。
ぼくも御多分に漏れず、高校生の時分から小林秀雄を読んだものの、実際のところ、自分とは縁遠い面白さしか、そこに見出すことは出来ませんでした。
けれど厳然として、“小林秀雄以来、日本には「カリスマ文藝評論家」とでもいうべき流れがあって、吉本隆明、柄谷行人らがこれに続いた。”と小谷野が書くように、日本の読書人はこの3人を圧倒的に支持し続けたのです。
そして丸谷才一の評論は、小谷野が評価する『後鳥羽院』や『日本文学史早わかり』は学問的にもしっかりしていたのでしょうが、それ以後、小谷野がふざけたものと指摘する『恋と女の日本文学』に至るまで、いまや文壇と読書人に圧倒的な勢力を築いているのも丸谷才一の置かれた状況なのです。
これにも当然、しかるべき理由があるのでしょう。
それを小谷野に分析してもらいたかったと思うのは、なにもぼくひとりに限ったことではないはずです。
本書で小谷野は、柄谷行人の『日本近代文学の起源』を比較的丁寧に読んでいるのですが、なかで傑作だったのは、落語好きの小谷野らしく、“柄谷の講演を聴いて、私は「暗い林家三平」だと思った”という一節です。
続けて小谷野は、こう記す。
“柄谷に学んで文藝評論家になった者たちは、その哲学指向のところばかり学んでいて、「フラ」がない。あるのは福田和也くらいだが、これはフラが多すぎる。”
これには笑った。
末筆ながら、この本(初版第1刷)、印刷の字が少し薄すぎないだろうか。




 Facebook [3ranjo]
Facebook [3ranjo] X(旧Twitter) @s_ranjo
X(旧Twitter) @s_ranjo Instagram
Instagram


 042-720-4644(留守電対応)
042-720-4644(留守電対応) 042-720-4644
042-720-4644