日本から正月らしさがどんどん消えていきますが、皆さんは、2003年のお正月をどんなぐあいにお過ごしになられたでしょうか。
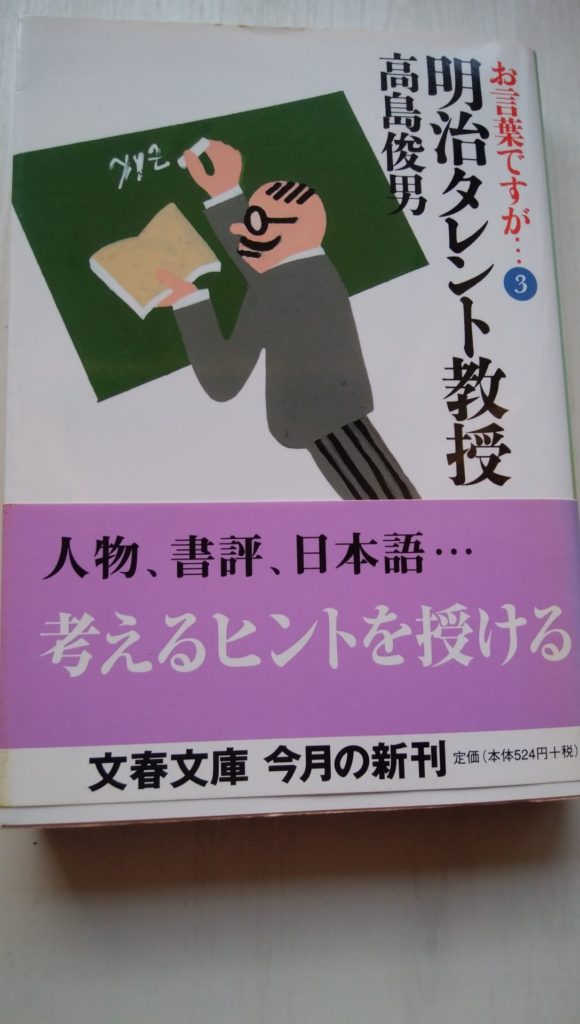
元日は初詣に行って、2日と3日は朝から箱根駅伝を見て、その後は、テレビで歌舞伎や寄席の中継を見ながら、ごろごろと寝正月、なんていう古きよき正月風景が、日本から駆逐されようとしています。
テレビの寄席中継は減少の一途を辿り、ついに民放はすべて撤退し、NHK1局限りとなってしまいましたし、西武百貨店はついにというか、とうとうというべきか、元日から営業を始めました。今までの経過からして、遅かれ早かれ他店も、元日から営業を始めることになるでしょう。
また、海外で過ごす観光客が増え、国際線の利用客は前年比11.8パーセント増の49万7600人と大きく伸び、米国同時多発テロ事件前の水準にほぼ戻りました。
このように、正月の日本からの人口流出はとどまるところを知りません。こうなればいっそのこと、正月もオリンピック並みに4年に1回の割合にすれば、少しはありがたみが増そうというものです。そうすれば、お年玉も4年に1回となり、渡すほうとしては、大助かりとなるのですが。
ぼくは、元旦は落語家として当然のことながら、師匠の御宅に伺い、お屠蘇を馳走になったのでした。師匠の御宅は足立区なので、町田からは結構遠いのです。まさに東京を南西から北東へ襷掛けのように、対角線上に横切るようなものですから、その長い車中は読書に当てるにはもってこいなのです。元日に読んだのが、「週刊文春」の名物コラム、本書『お言葉ですが…(3)』です。
高島俊男は一昨年、快著『漢字と日本人』(文春新書)を上梓し、目下絶好調の執筆活動を続けている中国文学者です。この『お言葉ですが…』も3冊目を数えましたが、ますます快調な筆捌きで、あたかも快刀乱麻を断つがごときです。一言、書名で触れなければいけないのは、本書は『明治タレント教授』となっていますが、この書名の単行本はありません。4年前に文藝春秋から同書が刊行されたときは、『せがれの凋落』という書名でしたが、文庫に収録するにあたり、この書名へと変更されたのです。
高島の本はいつもそうであるように、この本も含蓄をたっぷりと含んだ、じつにためになって、なおかつ面白い本です。
たとえば、“東京のことばが関西のことばにくらべてきつい感じがする理由の一つに、頭から濁ることばの多いことがあるんじゃなかろうかと思う”と、指摘していますが、なるほどなと思いましたね。
「アホ」をわれわれは「バカ」「ドジ」という。あるいは、「あかん」「あきまへん」を「だメだ」という。これでは、言われたほうは結構堪えますよね。
それはそもそも、日本語は頭から濁ることばが、一つもなかったことに由来するんだそうです。学校や文化とか道徳は、みんな頭から濁るのですが、これはすべて字音語、つまり外来語であって、純然たる日本語ではないのです。ですから、頭から濁ることばは、「した」と「べろ」のように、意味は強くなるけれど、総じて品が悪くなってしまう、というのですが、これには首肯するほかありませんでした。
なかでも笑ったのは、「何もありませんけど……」というタイトルのコラムでした。これは、明治時代いっぱい東大の総長を勤めた濱尾新の話。濱尾総長が外国のお客様を接待した時のこと。応接室でしばし話をしてから、総長は隣のへやを示しつつこう言った、とされています。
Please eat next room,there is nothing!
すなわち、「隣室を食べてください。そこには何もありません」という話。日本語をそのまま英語にして言えば通じると思ったところがいかにも濱尾総長らしい、というわけ。
ここを読んだときに、真っ先に思い出したのは、たしか阿川弘之が北杜夫との対談で言っていたと思うのですが、明治時代にある高名な英文学者が、ハワイの大学に招かれ、講演を英語で行ったところ、講演後の質疑応答で、地元の大学生がこういう感想をもらしたのだそうです。
「本日は長時間にわたっての講演をありがとうございました。もちろん、わたしは先生が何をおっしゃっているのか分かりませんでしたが、日本語が意外に英語に近いということがよく分かりました」と、挙手をして発言したのだそうです。
つまり、日本人の英語下手はこれはもう、今に始まったことではないということ。これを聞いて意を強くしたのは、なにもぼくばかりではないでしょう。
もうひとつ、爆笑ものに「せがれの凋落」があります。郵便局の窓口に、高島がお母様の満期になった証書をもちこんだところ、「あなたはこの高島ハナエさんの何ですか?」
「せがれです」
「それでは、証書の裏にせがれと書いてあなたの名前を書いてください」
つまり、いまや郵便局員は「せがれ」の意味を解さなくなっていると言う話。
おやおやとは思うものの、日本から正月らしさが消えていくのに比例して、言葉もどんどん消えていってしまう、という感慨を得た2003年の正月だったのでした。




 Facebook [3ranjo]
Facebook [3ranjo] X(旧Twitter) @s_ranjo
X(旧Twitter) @s_ranjo Instagram
Instagram


 042-720-4644(留守電対応)
042-720-4644(留守電対応) 042-720-4644
042-720-4644